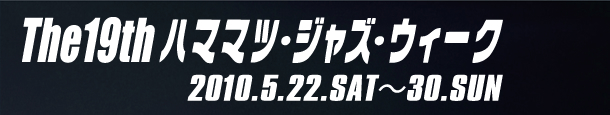| 日米を代表するミュージシャンが才気を競った、ここにしかないめぐり合い |
 |
| (文:長門竜也/ジャズライフ2010年8月号掲載) |
 |
| 街のライヴハウスはこの8日間、いくつもの注目バンドを登場させて熱気を高めていた。週末なら昼間も、駅前広場やデパートから生演奏の音が流れ、ここ浜松がすでにジャズのメッカであることを印象づけている。ホールに目を移すなら遠方より学生バンドが集ってコンテストを催し、一流アーティスト自ら壇上に立ってワークショップを開く。5月22日にスタートしたジャズ・ウィークの最終日、メイン会場において3時間を超すフィナーレが打ち上げられた。 |
 |
| ビッグバンド・ジャズの演奏で活気づく駅前北口広場の喧騒を横目に、街のランドマークタワー=アクトシティ浜松を目指す。8日間続いた第19回ハママツ・ジャズ・ウィークのフィナーレは、いつもその地下大ホールで開催される「ヤマハ・ジャズ・フェスティバル・イン・浜松」が飾ることになっている。当フェス開始当初より運営に尽力してきたDr. Jazzこと内田修氏が万全でないと聞く体調の中、今年も名誉顧問に立ったことが深く印象に残る。同じく第1回目から参加している佐藤允彦(p,comp)にとってライフワークとなったプレイズ・シリーズの対象者、故富樫雅彦もDr. Jazzが目をかけ世話をした最初の人物だった。そして佐藤が最初にこの盟友の作品に取り組み、ドイツのメールスにまでおもむいて初演したグループが、この日第1部に登場するSAIFAであったのを思えば、この連綿として長い循環が大いなる神の仕業と覚えなくもない。 |
| 広いステージの中央の舞台セットに、まずはひとりドラマーが現われ、マレットだけの荘厳なパフォーマンスを披露する。そこにパーカッションが加わり打楽器同士アンサンブルしたかと思えば、ベース、ピアノの順に下手から奏者を迎え入れ、淡いスウィング感を立ち昇らせていく。どれも巧妙にインプロヴァイズされた、上質の短編集を繙くようだ。また上手より6本の管楽器を引き込み、怪しく陽気なエスニック・サウンドを響かせた。 |
| 峰厚介(ts)の描く変則的で幾何学的フレイズの乱舞は、ペシミストにとって堪らない儚い輝きが仕込まれている。無機的なようで、放たれる直線音のひとつひとつに鮮明なグラデーションを感じる原朋直(tp)のプレイには、天才デザイナーの仕事をみる。リズムを鋭角的に捉え全身でそれを表現する小森慶子(bcl)、珠玉のメロディが塊になりそれを無限につなげていく山口真文(ss)、アウト・フレイズを4ビートでスウィングさせてしまう松本治(tb)、動物の雄叫びのような肉感的で直感的発音とスマートな構成力を捻出してみせる多田誠司(as)……。ギル・エヴァンス(p,arr)のようなクールな合奏を差し挟みながら、この目の眩むソロ群をたった冒頭の1曲へ濃縮させたステージには、ただ驚愕するしかない。静かでアラブ的な佐藤のピアノが、やはり民族的6/8リズムとアンサンブルの中で、憂鬱と官能の間を遊んでみせたのが「パピルス」。個々のメンバーもてんでの方角から腕力を奮ってくるが、派手なインタールードに一気に収束する……その様は大いに見ものだった。村上寛(ds)と和田啓(perc)のバトルも、ここでは民族楽器の交歓のように映る。いかにも佐藤らしいリフが多用されるのは「オウリッシュ・ペイサー」。木管の高域チームが奏でる怪しいひずみ音が鳴った途端、ホーン全体の急激なクレッシェンドがあり、瞬時にしんとした静寂が舞台を支配する。かと思えば細かい速射砲のトゥッティのあと、全員がダダをこねるようにアドリブでグズりだしたのには、つい笑わされてしまった。ランドゥーガ以来佐藤が試してきたその革新的コンダクトは、こういった曲でじつによく効果が発揮される。最終曲のタイトルは、秋田弁で「隠れて作った酒です」の意味だそうだ。一貫して陽気なドライヴ感の中、ソロ間に頻繁に挿入されるソリが毎回まったくイメージを変えて提示されることに気づく。これこそ、当テンテットに対する佐藤のこだわりの凝縮なのではないか。過激なユニゾン・アンサンブルがめまぐるしく披露され、このステージも幕が引かれた。 |
 |
| 続いて、もはやジャズで括ることのできなくなった、独自のヴォーカル・ワールドを構築するakiko(vo)。フィンガー・スナップに合わせオルガンのフット・ベースとドラムのブラシが出現させたダークな空気が、やがて会場中に蔓延する。 |
| 先刻急逝したGURU(JAZZMATAZZ)への追悼か、彼がラップで一気にまくしたてたジャズの歴史を、akikoの声は重厚な「ホワッツ・ジャズ?」のサウンドの中で優雅に泳がせた。この日がスウィングの王様ベニー・グッドマンの101歳の誕生日であることも、この選曲と何か関連があったろうか。リズムは続き、そこにMCを乗せて軽快な「オールド・デヴィル・ムーン」へ導く手際も心得たもの。その終盤には、パーカッシヴな江藤良人(ds)のプレイにスキャットを絡ませたが、それがじつに聴きものとなった。金子雄太(org)がオルゴールのようなミニ・ピアノを扱う次曲は、やがて澄んだアカペラに引き継がれ、それが「ノルウェーの森」だと知らされる。効果的なサウンドがその声を覆ってしまうと深閑とした森が目の前に出現し、エスニックな宗教感とクラブ系のトランス感で全体が包まれていく。かと思えば、教会でオルガンが奏でられるような自作R&Bナンバー「アイ・ミス・ユー」が始まると、akikoは舌足らずなルーズ・シンギングを完璧にこなしてみせる。ジャジーなスキャットがあり、スウィンギーなカズーがあり、観衆の誰もがこの3者の創り出す目映い世界に引き込まれていった。 |
 |
| そして大トリをつとめるのは、マイク・スターン(g)の超絶技巧トリオ。リハーサルの続きのようにスターンが楽器を弄んでいたかと思うと、それがもう曲へのカウントだったらしく、メンバーはみごと同期して重厚なグルーヴを開扉させた。驚く間もなく、いつものあのスターン節が軽やかに闊歩し、躍動感に満ちた連続的フレイズはリズムとの応酬へと転じていく。初めはそのことに耳を奪われて気づきもしないが、これがスタンダード曲の「ソフトリー・アズ・イン・ア・モーニング・サンライズ」だと徐々に明らかにされる。この手際がさり気なさすぎて、もはや憎らしいほど。クリス・ミン・ドーキー(b)のサイレントベースは重くスピリチュアルに構えていたが、ソロを受け、バンドがエモーショナルにヒート・アップしていくと唸るような力感を前面にし始める。速射砲のようなギターが、その熱気を次はドラムへ受け渡す。と、導入部では心地よい歌心を醸したデイヴ・ウェックルだが、名にしおう千手観音ぶりが頭をもたげてからは、冴えわたる皮と金属のひっきりない打音で、観客もみな脳がくらくら状態に。とてもこれが気怠いあの有名ミュージカル曲とは思えない。輪をかけてファンク色が高まりハードコアなロック・ビートで表現された「KT」は、奇妙奇天烈なテーマ構成で驚かされ、その中で怖ろしいほどのロック・ギタリスト然として没頭した歓喜のペンタトニック・ソロは、決して忘れられないだろう。重いリズムが生じR&Bスタイルになると背後の幕が上がり、そこに控えていたSAIFAの面々がスポンテイニアスなホーンを響かせる。これが信じられないことにスターンの音楽と思わぬ角度で密着して化学反応を起こし、深淵さを倍にも増加させることになった。単純に編曲の妙ともと思えないし、まったくの即興のわけもない。ここでは棒振りに徹する佐藤が用意してきたいくつかのサウンド・イメージを、指揮者の采配に従い全員が巧妙にアンサンブルしているのだ。目前に繰り広げられる音のマジックに観衆は思わず息を飲み、羨望の眼差しを向け、こみ上げてくる情感を押さえるのに精一杯の様子。みな同じ気持ちだったのだと思う。スターンはこの実験の成功を受け、終演とともに舞台中央で大きくガッツ・ポーズをとってみせたのだった。 |